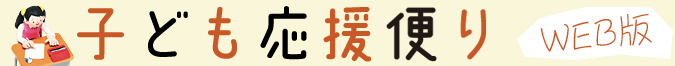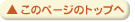- 自分にできることを考え行動を
- 日本原水爆被害者団体協議会 事務局次長
和田征子さん

和田 征子(わだ まさこ)
1943年長崎市生まれ。日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)事務局次長。被爆当時は1歳10カ月。活水女子短期大学と明治学院大学を卒業後、英語教員として勤務。1977年からの約5年間はアメリカで生活。2015年から日本被団協の役員を務め、国内外で被爆体験を語り続けている。24年に日本被団協がノーベル平和賞を受賞した際、被爆者の存在を世界に知らしめた喜びを語った。同年からは「核兵器をなくす日本キャンペーン」の副代表理事も兼任。核兵器廃絶活動の最前線に立ち続けている。
――証言活動を始めたきっかけを教えてください。
被爆者である自覚はずっとありましたが、若い頃は積極的に活動することはありませんでした。意識が変わるきっかけとなったのは、夫の仕事の関係でアメリカのカリフォルニア州に1977年から住んだことです。そこでは移民として渡米し、苦労をされた一世の方々との出会いがありました。41年の開戦後、全てを残して日系人は敵国民として遠い砂漠の中の収容所に送られました。アメリカ兵としてヨーロッパ戦線に送られ、息子を亡くした家族もある。そんな中で私は自分が被爆者だと話すことはできませんでした。でも、だからこそ帰国後に「このままではいけない、原爆の事実を伝えなければ」という強い思いにかられました。
――証言活動を行う上で、大切にしていることは?
「話を盛らない」ということです。伝聞や個人的な感情を加えずに、母から聞いたことを脚色なく話す。それが私が聞いた「実相」だからです。私は1歳10カ月で被爆したので、当時の記憶はありません。物心がついた頃から、母やその友人たちの間で交わされる原爆の話題を自然と耳にして育ちました。かつて、母から聞いた話をまとめた文章を母に読んでもらったことがあります。すると母は、「こんげんもんじゃなか(こんなもんじゃない)」と一言。記憶のない自分が証言することに、ためらいを感じるようになっていきました。そんな中、2016年に国連の会議で、サーロー節子さんにお会いした際にその気持ちを打ち明けると、「お母様の話を聞きながら育ったあなたはいろんなことを知っているのだから話していいのよ。あなたのような若い人が話してくれる方が嬉しい」と背中を押されました。
この言葉がきっかけとなり、多くの被爆者の証言に触れ、知識を深めるうちに、話す内容は同じでも、思いの強さが変わってきました。世界中の先達が何十年もかけてやってきたこと、「これは世界のためになることなんだ」と確信し、証言活動を続けています。
――子どもたちに伝える時、どんな工夫をしていますか?
子どもたちに話す時には、こんなお話をします。
「仲良くしようと遊びに行く時に、ポケットにアメは入れていっても、石は持っていかないよね?それと同じだよ。本当に仲良くしたいなら、いらないものは捨てて、いいものだけを持っていくはずだよね」
本当に平和を望むなら、備えるのではなく、仲良くする方法を考えるべきです。たとえ、自分に不利なことがあるとしても、自分のことだけを考えずに、相手のことも考えてもらいたいのです。それが核兵器禁止条約の根本にも通じる「公共の良心」という考え方です。
オスロのノーベル平和センター前の敷石には南アフリカ共和国のネルソン・マンデラ元大統領の言葉が刻まれています。「最強の武器は、座って話すこと」、つまり「対話」であると。暴力ではなく、対話で解決してもらいたいと思います。
――教職員や保護者へのメッセージをお願いします。
ある国の大使に、「唯一の被爆国である日本では、どんな平和教育がされていますか?」と聞かれたことがあります。残念ながら、日本の平和教育は教職員の意識の高さに頼る部分が大きく、広島や長崎とそれ以外の地域では、温度差があるのが現状ですよね。戦争が一人で始められないように、平和活動もまた一人ではできません。多くの人々の協力によって、被爆者の思いが伝え続けられてきたからこそ、今があります。教職員のみなさまには、この平和のバトンを次世代につないでいく役割を担っていただきたいと思います。
「今日の聞き手は明日の語り手」という言葉があります。学校で話を聞いた子どもたちが、家に帰って保護者に話す。そうやって、小さな行動が次の行動へとつながっていくことが、とても重要だと考えています。