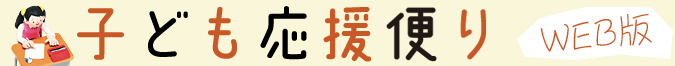- 学校はもっと楽しくなる
- 大阪市立大空小学校 初代校長
木村 泰子さん

木村 泰子(きむら やすこ)
大阪生まれ。武庫川学院女子短期大学(現・武庫川女子大学短期大学部)卒業。2006年に開校した大阪市立大空小学校校長を9年間務め、障害の有無にかかわらず「全ての子どもの学習権を保障する」という理念で学校づくりを行った。そのドキュメンタリー映画『みんなの学校』が2015年に公開され、大きな反響を呼び、現在も各地で自主上映会が開催されている。退職後は講演活動やセミナーで全国を飛び回る多忙な日々。著書に『「ふつうの子」なんて、どこにもいない』(家の光協会)『「ほんとのこと」は、親にはいえない』(同)、共著に『学校の未来はここから始まる』(教育開発研究所)がある。
――木村先生に憧れる教職員は多いと思います。
実は、私は小学校の教員志望ではありませんでした。運動が大好きだったので、中学校の体育の先生になりたかったのです。でも、人生の偶然とでも言うのでしょうか、中学校に空きがなく、腰掛けのつもりで行った小学校で、子どもたちと出会ったその日から45年間、一度も迷うことなく小学校の教員を務めることになりました。
よく「学校の先生になりたいけど、自分に合っているか不安」という話を聞きますが、志望の段階で「教員」という仕事の本質など、ほとんどの人が分かっていないし、ある意味、それでいいのだと思っています。なぜなら「どうして教員になるの?」というのは自分が主語ですが、学校での主語は目の前の子どもです。30人の子どもがいたら、30通りの主語があります。そこではじめて「教員の仕事って何?」という自問が始まるのですから。
――職場としての学校についてはどう考えますか?
最近は、大学の教職課程で学ぶうちに志望職種を変える人が増えているようです。また、夢を抱いて教員になった人ほど辞めていく、と聞きます。多忙化の問題がよく指摘されますが、背景として学校の古い組織文化の存在も大きいと思います。一つ目は、上意下達のヒエラルキー。二つ目は前例の踏襲。そして、三つ目が周囲からの同調圧力です。これらが、学校を職場として見た時、若い人たちに不自由を感じさせ、なじまなくさせているのでしょう。
それでも今、あえて若い世代に言いたいのです。それこそ文科省が新しい学習指導要領で打ち出している「主体的・対話的で深い学び」を教職員も実践して、学校を変えることができる時です。
――そうするために、教職員に何が必要でしょうか?
まず、しっかり理解しておいてもらいたいのは、教職員の給料は、校長や教育委員会にもらっているのではないということ。校長時代は職員室でよく話したものです。
「あんたらの給料はそもそも税金やろ? 顔を向ける方向は一人ひとりの子どもやろ?」
教職員が何より気にするべきなのは、目の前の子どもたちが安心して学んでいるかどうか、という事実です。それが教職員の仕事の根幹です。
子どもが自分らしくありのままに過ごし、ときには友だちとぶつかる。そこで起きたトラブルを生きた学びに変えていく。これが10年先、20年先の生きて働く力になるわけで、そのことに気が付いている先生がいる学校はどんどん変わっていきます。大事なのはどう指導するかよりも、より良い教室の空気、学校の環境をつくることです。
――保護者や地域の皆さんの力も必要ですよね?
保護者は誰でも自分の子どもの成長を願うものです。でも「自分の子どもに育ってほしければ、周りの子どもを育てにおいでや」と言い続けたのが大空小学校です。そういうことも含め、「みんなの学校」なんです。
学校に立ち寄った時に、困っている子がいたら、自分の子は放っておいても、「大丈夫?」と寄り添ってあげる。そうすれば子どもは誰も逃げていきません。友だちをなぐっている子どもがいても「暴力はあかんよ」とは言いません。「大丈夫?」と問いかけるのです。すると暴力をやめるのに、「なぐったらあかん」と言うと、もっとひどくなる。それが子どもだ、ということを保護者たちは身をもって学んでいきました。
周りの子どもが育てば、環境が豊かになるのだから、必然的に自分の子どもも育ちます。これをおとなのチーム力と呼んでいます。子育ては、ギブ&テイクではなくウィン・ウィンで、と。
最初は一人の保護者のまさに主体的な行動が始まりでした。だから、先生方も保護者も地域の皆さんも、一人ひとりの子どもを主語にして行動を起こせば、その地域で学校を変えることができると思うんです。もちろん、それは自分自身を元気にしたり、幸せにしたりすることでもあります。