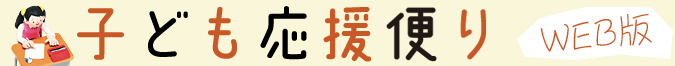- どんな苦難も乗り越えられる
- エッセイスト
安藤和津さん

安藤和津(あんどう かづ)
1948年東京都生まれ。エッセイスト。上智大学卒業後、イギリスに2年間留学。その後、CNNメインキャスターを経て、ラジオ・テレビで司会やリポーターを務める。1979年に、俳優・映画監督の奥田瑛二と結婚。長女は映画監督の安藤桃子、次女は俳優の安藤サクラ。実母の在宅介護をきっかけにうつ病を患いその後、寛解。その経験を綴った『“介護後うつ"「透明な箱」脱出までの13年間』を昨年刊行した。その他の著書に『愛すること愛されること』『オムツをはいたママ』など。
――ご自身の子ども時代について教えてください。
母は仕事が忙しく、私は乳母に育てられました。「あれは駄目、これはしちゃいけない」と、あらゆる危険から遠ざけられ、必要な物が全て用意された環境でお姫様のような幼少期を過ごしました。それが母の愛情であることはわかりましたが、おかげで小学生の頃は虚弱体質で、仲間はずれにされたりいじめられたり、辛い思い出が多いです。ですから、物心がついた時には「親になったら、正反対の方法で子育てしたい」と思うようになりました。
二人の娘には、自ら創意工夫する力を養ってもらいたいと、のびのび成長できる環境を与えたつもりです。生きる上で必要な力は、自分自身で楽しさを見つけ表現すること、つまり、イマジネーション(想像力)とクリエイティビティー(創造力)だと考えています。長い人生には悲しいこともあるけれど、それ以上に楽しいことが山ほどあることを知ってもらいたい。そのためのアンテナを持ってもらいたい。そうすれば、どんな苦難でも乗り越えることができます。それが「人間力」だと思うのです。
――近年、お子さん方が各分野でご活躍されています。
長女の安藤桃子は映画監督、次女の安藤サクラは俳優という道を選びましたが、それに関して口をはさんだことはありません。ただ、何かを表現する人になってくれたらいいなという期待はありました。毎晩のように娘たちと、自由に物語をつくって遊んだのですが、当時から、姉の桃子は奇想天外なストーリーを考えるのが上手で、妹のサクラは声色を使い分けて役を演じるのがうまかったです。サクラが4歳の頃、舞台で稽古中の奥田を見て「サクちゃん、あれになる!」と宣言したことが今も印象に残っています。
――お母様の介護を契機に13年におよぶ「介護うつ」を経験されました。
脳腫瘍、認知症、老人性うつを患った母を自宅で介護しました。眠れない、食べられない日々が続いて追い詰められ、ほこりが少しずつ溜まるようにして体と心のバランスを失っていきました。病院でうつ病の診断を受け、数年後に母が亡くなってからも、状況は改善しませんでした。完全に抜け出したのは一昨年です。
介護に疲れきっていた当時の私や、同じ境遇に置かれている人に声をかけるなら「頑張らなきゃという気持ちを捨てて下さい」とアドバイスします。たとえ愛する家族の介護であっても、自分を犠牲にするのは間違いです。介護される側もそんなことは望んでいません。歯を食いしばって眉間にしわを寄せるような介護はしてはいけません。
うつから抜け出す大きなきっかけになったのは、孫たちの存在でした。オムツ替え、入浴や着替えの介助など、することは高齢者の介護と変わりません。ですが、待ち受ける死を否応なく意識させられる介護と、生命力の塊のような赤ちゃんの世話は、まるで別物でした。何より、孫を世話するうちで亡くなった母の存在を感じる瞬間があったのです。「足の形が似ている」「笑顔がそっくり」だなど、母がこの世に生きていた証が私と娘を経て孫にまで受け継がれていると実感した時、喪失感が希望に変わりました。
――家庭や学校など、教育を取り巻く現状についてどのようにお考えですか。
人を育てるということは生半可なことではありません。保護者や先生だって生身の人間です。たった一人で全部を背負い込んでは、疲れ果ててしまいます。時には、一人の時間を作って自分を取り戻すことも大切でしょう。そのためには、友人や地域のネットワークなど、利用できるものは全て利用してください。地域ぐるみで子育てを助け合う仕組みがもっと広がることを期待します。
未来を担う子どもたちは、かけがえのない宝物です。次の時代を生きる子どもたちを育てるには、家庭、学校、地域社会が互いに協力し合うことが肝心です。みんな誰かの助けを借りて大きくなったのですから、その恩返しをするのが本来の姿なのではないでしょうか。