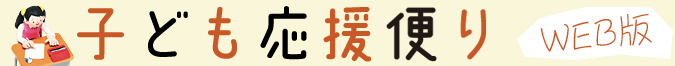- 確実に登れる道が見つかる
- 元マラソン選手
有森裕子さん

有森 裕子
1966年岡山県生まれ。90年、マラソン初レースとなった大阪国際マラソンで、当時の初マラソン日本女子最高記録を樹立。92年のバルセロナ五輪で、日本女子マラソン初の銀メダルを獲得。96年のアトランタ五輪でも銅メダルを獲得した。現在は、自らが設立したNPO「ハート・オブ・ゴールド」やアスリートのマネジメント会社「ライツ(現 ㈱RIGHTS.)」で活動するかたわら、市民ランナーとして世界各地の大会に参加。ほか、スペシャルオリンピックス日本理事長、日本プロサッカーリーグ理事、厚生労働省いきいき健康大使なども務め、幅広いフィールドで活躍している。
――陸上を始めたきっかけを教えてください。
私は陸上を好きではじめたわけではありません。生後二カ月で両足股関節脱臼と診断され、乳幼児期はギプスをはめて生活していました。小学生の頃には徐々に改善されたものの、O脚の足がうまく曲がらず、走る時も体が傾き、よく転んでいました。「自分はみんなとは違う」。他人と比べて自信を持てずにいた5年生の頃、陸上クラブの先生が、「みんな違っていい。違いこそ武器なんだ。それを活かせるものを探そう」と言ってくれたのです。中学校の運動会では、みんなが敬遠する長距離の800m走にエントリーして、「人生初の一着」をとりました。それを機に陸上の強豪校に進学し、本格的に陸上を始めることになったのです。
――陸上が好きでなくても続けられたのですか?
「得意=好き」であるとは限りません。唯一、私が得意なことは、「人より頑張ること」でした。いつも「もうダメだ」と思ったら、「あと少しだけ」ともうひと頑張りしてみる。そうしているうちに、少しずつ、記録が伸びていったのです。母親はよく私に、「眉の上の高さくらいの目標を立てなさい」と言っていました。いきなり大きな目標を達成するのは難しいけれど、眉の上、ほんの少し上の目標なら達成することができるという意味です。そうした小さな成功の積み重ねが、五輪での二大会連続メダル獲得につながったのだと思います。
――現在の子どもたちを見て感じることは?
何かをやり始めても、嫌になったらすぐに諦めてしまう傾向があると感じます。わが子のできない様子を見たくない保護者が、「嫌なら辞めていいよ」と薦めるということもあるようです。「何でできないんだろう」と悩むこともあるでしょうが、向き不向きは、本気で打ち込んだ人にしかわかりません。登山でいえば、急な斜面で登れないと判断しても、登ることを諦めなければ、遠回りでも確実に登れる道が見つかる、というように別の選択肢が見つかるかもしれません。
現役時代、ケガで走れなかった時、小出義雄監督の「何でと思うな、せっかくと思え」という言葉が救ってくれました。「何でケガをしたんだろう」と思ってもよくはなりません。それなら、「せっかくケガをしたのだから、ゆっくり休もう」と考えることで、精神的にも楽になったのです。「せっかく」の経験を無駄にしないためにも、一度始めたら諦めずに最後までやりきってほしいです。
――子育てに奮闘する保護者や教職員にメッセージを。
イベントや講演会など、人前で経験を伝える際、「話す」のではなく、「語る」ように心がけています。「話」という字は、「舌で言う」と書きます。つまり、口で言うだけ。それに対して、「語」は、「吾(われ)を言う」です。一方的に話すのではなく、自分の考えを加えて対話するイメージです。先生と子どもの関係も同様ではないでしょうか。教科書は同じでも、どう伝えるかで違いが生じてきます。
海外に比べて、日本の先生は、子どもたちと接する以外の業務時間が長いという調査結果が出ています。余裕がないため、「早く伝えなければ」と焦ることも多いでしょうが、「今日は予定通りに授業が進まなかった」という日があってもいいと思います。子どもたちの体調や気持ちは日々変化します。授業に絶対的な正解はないのですから。
いじめ等の問題が発覚すると、全責任が学校にあるかのようにマスコミで報じられることがあります。「なぜ先生はいじめに気付けないの?」と思う保護者もいるでしょうが、マンツーマンで向き合える親子と違って、先生は40人近い子どもたちを一人で抱えているのです。また、おとなに問い詰められたら、なかなか正直に話せないのが子ども。どうしたら真意を汲み取ることができるかを考えて接することが大切です。家庭と学校、保護者と教職員が互いにできることを分担・協力し、子どもたちの成長を支えていってもらえたらと願います。