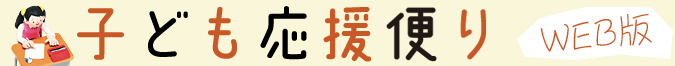- 学ぶ場所は家庭です
- 作家・高野山真言宗僧侶
家田荘子さん

家田荘子
作家・高野山真言宗僧侶・高野山高等学校特任講師。愛知県出身。日大芸術学部放送学科を卒業後、OLを経てフリーライターに転職。1991年に「私を抱いてそしてキスして エイズ患者と過ごした一年の壮絶記録」で第22回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。「極道の妻たち」をはじめ「歌舞伎町シノギの人々」、「四国八十八ヵ所つなぎ遍路」など、著作は129作品にのぼる。ノンフィクション作品の他、コミックの原作や恋愛エッセー、小説にも定評がある。近年は、全国の小中学校などで、子どもやPTAを対象にした講演会も精力的に行っている。
――子どもの頃はどう過ごされたのでしょうか。
銀行員の家庭に育ち、小学校時代は、体育以外オール5という典型的な優等生でした。母親に厳しく育てられ、テストで90点未満だと殴られるのは当たり前。一度も褒められた記憶がありません。
母は勉強もスポーツもできる優秀な人。性格も明るく友人が多く、学校の先生にも母の同級生が何人もいました。私は性格が暗く、どんくさい。いつも比較されて大変でした。それに父の転勤で転校を繰り返したため、友達もできず、いじめられたこともありました。
――いじめのことは、親や先生に相談しましたか。
なかなか話せませんでした。いじめていたのは、おとなから見て「良い子」に映る子どもたちです。人の見ていないところでいじめるので、先生も気づかず、相談したところで信じてもらえるとは思いませんでした。時には存在を否定されるようなことも言われ、自殺を考えたこともあります。
厳しい母も、この時ばかりは同情してくれるだろうと相談しましたが、「いじめられる方も悪い」とぴしゃり。当時は寂しかったですが、母の厳しさがなければ、後にマスコミ業界の激しい競争の中で生き残れなかったとも感じます。
――元々は女優志望だったそうですね。
暗い性格を変えたくて、「女優ならいろんな役ができて、別の自分になれる」と憧れていました。高校時代から、ドラマなどに出演しています。でも、地元愛知では小さな役しかもらえませんでした。
大学進学を機に上京。パンクファッションと踊りが好きで、卒業後、六本木で遊んでいました。女優として雑誌に売り込みに行った時、六本木の事情を話していたら、「書いてごらん」と。これが作家デビューのきっかけです。この業界なら女優としてのチャンスも、と思いましたが、「極妻」の五社英雄監督に「才能ないね」と言われ、諦めました。
――それで作家への道を?
取材は、人と関わるのが苦手な自分には向かない仕事だと感じていました。一度で取材が終わらず年単位に及んだり、取材依頼の電話ができずに何カ月も過ごしてしまったり。それで、「話し下手な自分にもできることは」と考えた末、思い立ったのが「聞き上手になる」でした。下手な話をやめると、相手が語ってくれるようになりました。発想の転換で、コンプレックスを逆に利用できたのです。
――今の子どもたちを見て感じることは?
とにかく打たれ弱い。「逆境」を乗り越えれば一回り強くなれるのに、親がそれをさせず、一歩手前で手を差し伸べてしまう。おとなたちに「一緒に乗り越えよう!」という気概が足りないのかも知れません。
あいさつもできないですね。あいさつは、コミュニケーションのきっかけとして重要です。顔を見てあいさつすることで、相手のほんのわずかな変化も気付くようになります。
――子育て中の保護者や学校の先生へのメッセージをお願いします。
子どもはおとなの言動をまねします。ある時、街で子どもがぶつかってきそうだったので避けると、「ありがとう」も「ごめんなさい」もない。後ろから来た親も何も言わないのです。何か問題が起きると、学校や先生の責任が問われがちですが、そもそも、子どもが初めて学ぶ場所は家庭です。そこにDVやののしり合いがあれば、子どもは言葉や暴力で人を支配する方法を学んでしまいます。
今の子はお芝居がとても上手なので、先生がいじめに気付かなかったとしても仕方ありません。ただ、発覚した時は、力を合わせて対処してほしいと思います。
取材で知り合った、少年院の子どもたちが言っていました。「親や先生がしっかり話を聞いてくれたら、ここに来ることはなかった」。強く印象に残っています。「ウチの子は大丈夫」と高をくくらず、子どもが何かを伝えようとしている時には、「忙しい」「後にして」などと言わず、必ず話を聞いてあげてください。